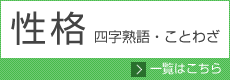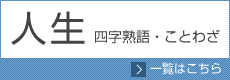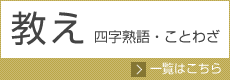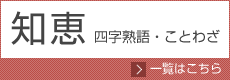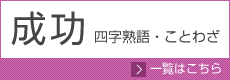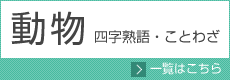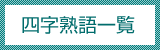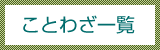足元から火がつく(あしもとからひがつく)
スポンサーリンク
- 【意味】
- 災難や危険が身の回りで起こり、身に迫ること。
- 【用例】
「ことばライブラリー」は、四字熟語とことわざの一覧、それらの意味と用例を掲載しております。 四字熟語とことわざの教材や習い事(スクール)の材料として、またあらゆるビジネスシーンや学校、日常生活での知識・検索、ネタなどにどうぞ。 他に受験・漢字検定などの試験、漢字の意味、辞書・辞典、慣用句辞典、反対語、対義語、名言、座右の銘、類義語などの参考にもご活用くださいませ。
 逆引き四字熟語・ことわざ検索
逆引き四字熟語・ことわざ検索
スポンサーリンク
 【その他の四字熟語・ことわざ】
【その他の四字熟語・ことわざ】
- 天神地祇(てんしんちぎ)
- 天に眼(てんにまなこ)
- 死屍累累(ししるいるい)
- 管を以て天を窺う(くだをもっててんをうかがう)
- 暗夜に灯火失う(あんやにともしびうしなう)
- 片言隻句(へんげんせきく)
- 電光石火(でんこうせっか)
- 一致団結(いっちだんけつ)
- 洛陽紙価(らくようのしか)
- カエサルの物はカエサルに(かえさるのものはかえさるに)
- 伴食宰相(ばんしょくさいしょう)
- 浅酌低唱(せんしゃくていしょう)
- 地獄も住みか(じごくもすみか)
- 花より団子(はなよりだんご)
- 知らぬ顔の半兵衛(しらぬかおのはんべえ)
- 鴛鴦の契り(えんおうのちぎり)
- 時期尚早(じきしょうそう)
- 手前味噌を並べる(てまえみそをならべる)
- 一寸先は闇(いっすんさきはやみ)
- 地蔵は言わぬがわれ言うな(じぞうはいわぬがわれいうな)
スポンサーリンク