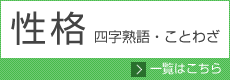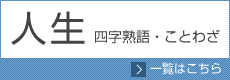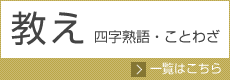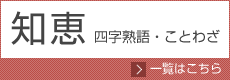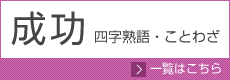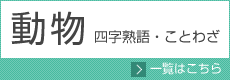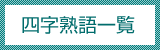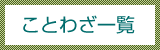牛耳を執る(ぎゅうじをとる)
スポンサーリンク
- 【意味】
- 中国の春秋戦国時代、諸侯が盟約するときに、盟主となる人物が牛の耳を裂いて出した血を順番にすすり、かたく誓い合ったという話から、集団・団体・同盟などの組織の首領や支配者になるということ。組織などの主導権を握り、自分の思うままに動かすということ。牛耳る。
- 【用例】
- このグループには正式なリーダーがいるが、実質的に牛耳を執っているのは彼女だ。
「ことばライブラリー」は、四字熟語とことわざの一覧、それらの意味と用例を掲載しております。 四字熟語とことわざの教材や習い事(スクール)の材料として、またあらゆるビジネスシーンや学校、日常生活での知識・検索、ネタなどにどうぞ。 他に受験・漢字検定などの試験、漢字の意味、辞書・辞典、慣用句辞典、反対語、対義語、名言、座右の銘、類義語などの参考にもご活用くださいませ。
 逆引き四字熟語・ことわざ検索
逆引き四字熟語・ことわざ検索
スポンサーリンク
 【その他の四字熟語・ことわざ】
【その他の四字熟語・ことわざ】
- 少年老い易く学成り難し(しょうねんおいやすくがくなりがたし)
- 漱石枕流(そうせきちんりゅう)
- 断章取義(だんしょうしゅぎ)
- 雀百まで踊り忘れず(すずめひゃくまでおどりわすれず)
- 百折不撓(ひゃくせつふとう)
- 子の心親知らず(このこころおやしらず)
- 管鮑の交わり(かんぽうのまじわり)
- 出藍の誉れ(しゅつらんのほまれ)
- 克己復礼(こっきふくれい)
- 眼光紙背(がんこうしはい)
- 抜本塞源(ばっぽんそくげん)
- 同病相憐れむ(どうびょうあいあわれむ)
- 隠忍自重(いんにんじちょう)
- 志操堅固(しそうけんご)
- 奇想天外(きそうてんがい)
- 一心同体(いっしんどうたい)
- 頭押さえりゃ尻ゃあがる(あたまおさえりゃしりゃあがる)
- 窮鼠猫を噛む(きゅうそねこをかむ)
- 社交辞令(しゃこうじれい)
- 手も足も出ない(もあしもでない)
スポンサーリンク