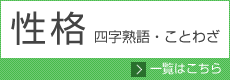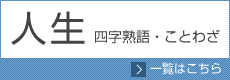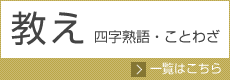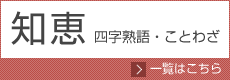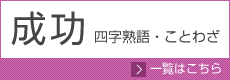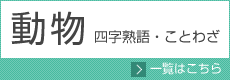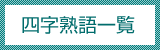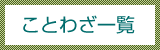閑古鳥が鳴く(かんこどりがなく)
スポンサーリンク
- 【意味】
- 「閑古鳥」とは鳥の郭公(かっこう)のことで、静かな山里で郭公が鳴く様子が寂しく感じることから、訪れる人もなく、ひっそりと静まり返って、もの寂しい様子のこと。客が来ず、商売が繁盛していないこと。
- 【用例】
- 不景気のせいか、ここのところ毎日店に閑古鳥が鳴いている。
「ことばライブラリー」は、四字熟語とことわざの一覧、それらの意味と用例を掲載しております。 四字熟語とことわざの教材や習い事(スクール)の材料として、またあらゆるビジネスシーンや学校、日常生活での知識・検索、ネタなどにどうぞ。 他に受験・漢字検定などの試験、漢字の意味、辞書・辞典、慣用句辞典、反対語、対義語、名言、座右の銘、類義語などの参考にもご活用くださいませ。
 逆引き四字熟語・ことわざ検索
逆引き四字熟語・ことわざ検索
スポンサーリンク
 【その他の四字熟語・ことわざ】
【その他の四字熟語・ことわざ】
- 人は一代 名は末代(ひとはいちだい なはまつだい)
- 情状酌量(じょじょうしゃくりょう)
- 転んでもただでは起きぬ(ころんでもただではおきぬ)
- 轍鮒之急(てっぷのきゅう)
- 人参飲んで首くくる(にんじんのんでくびくくる)
- 良薬口に苦し(りょうやくくちににがし)
- お山の大将俺一人(おやまのたいしょうおれひとり)
- 物は言いよう(ものはいいよう)
- 少年老い易く学成り難し(しょうねんおいやすくがくなりがたし)
- 女房と畳は新しいほうがよい(にょうぼうとたたみはあたらしいほうがよい)
- 螻蛄才(けらざい)
- 修身斉家(しゅうしんせいか)
- 抜け駆けの功名(ぬけがけのこうみょう)
- 烏合の衆(うごうのしゅう)
- 呉越同舟(ごえつどうしゅう)
- 立つ鳥跡を濁さず(たつとりあとをにごさず)
- 開口一番(かいこういちばん)
- 水に流す(みずにながす)
- 炒り豆に花(いりまめにはな)
- 古今無双(ここんむそう)
スポンサーリンク